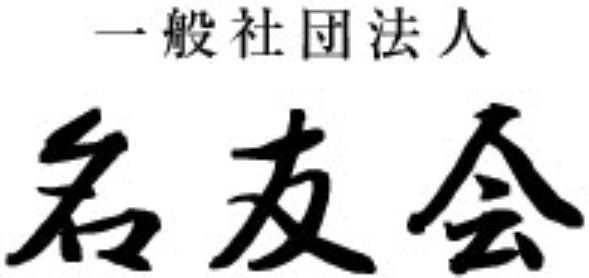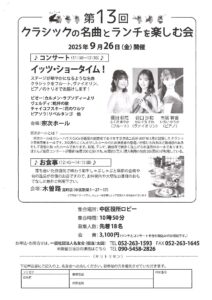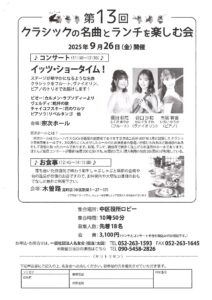名友報127号「夏のクイズ」解答と講評

名友報127号「夏のクイズ」に多数のご応募をいただきました。ありがとうございました。コロナ禍以降、クイズの応募者が逓減傾向にあります。問題が難しいとかマニアックだとか、様々なご意見をいただいております。難易については、回答者の状況にもよるでしょうが、「高齢者の頭の体操」を基本に、いろいろな「頭の使い方」を引き出していきたいと考えて、現在の出題パターンにいたっております。昔、学校で覚えた知識だけで解答できる問題はできるだけ避けて、たまたま接しえた知識に当たれば儲けもの、という感覚で出題をしております。
最近は、インターネットの検索機能を利用される方も多いようです。出題者も何かと頭を回して問題を作成していますが、回答者も、あの手この手で調べていただければ、頭の体操になるかと思います。
今号のクイズは、いくらか配慮した結果、応募者全員が正解ということに。これは初めてでした。問2の答えはいくつかに分かれましたが、結果として15㎝が引ければ正解としました。「最短」とは書かなかったので。
それでは、各問の解答です。
第1問
次の文章は、日本の著名な作家の説明をしたものです。作家名とその作家が直木賞を受賞したときの著作名を正しく答えてください。
名古屋市中区に生まれ、名古屋で作家活動、同人活動をし、愛知学芸大学(当時)で教鞭をとっていたことがある。神奈川県の茅ケ崎市に転居しても、名古屋に通勤していたが、その通勤時間が著作の時間だと言っていた。経済小説が評判となったが、歴史小説の分野で、テレビドラマや映画の原作となった作品も多い。東区白壁に「書斎」の一部が再現されている。
正解は 作家名「城山 三郎」 作品名「総会屋錦城」
東区白壁地区文化のみちゾーンに、文化のみち「二葉館」が整備されたのは平成17年2月8日、今年で20周年となります。電力王福沢桃介と川上貞奴が暮らした「二葉御殿」と呼ばれた建物を、名古屋市が寄贈を受け、活用策を検討する中で、文化のみちゾーンに復元、再配置することとなりました。一方、名古屋市出身の直木賞作家城山三郎氏から所蔵の書物などの寄贈を受け、その活用法を検討していたのが当時の市民経済局。当時の市長の「鶴の一声」で、「二葉御殿」の2階部分で、そのできる範囲で進めるよう指示がありました。
当時としてはモダンな和洋折衷の2階建て、その2階部分を使って、城山三郎氏の所蔵品の展示公開を含め、小さいながら名古屋だけでなく広く東海地方の「文学館」を目指して整備することとなりました。当時、城山氏はご健在で活躍中だったので、特定の個人名を冠しての施設は適切でないことから、「郷土の文学資料室」として、
1 郷土ゆかりの文学(愛知・岐阜・三重・静岡の西部を意識)
2 同人誌(収集するのではなく寄贈による)
3 城山三郎氏の所蔵品(書斎の再現を含む)
の3本の柱でスタートしました。郷土は、範囲をあいまいにしていますが、愛知県を中心に岐阜・三重・静岡あたりまでは視野に入れています。郷土の文学者としては、小谷剛(名古屋)、江夏美好(岐阜)、江戸川乱歩(三重)などを意識していましたが、開館前に、短歌の春日井健氏のご遺族から所持品を寄贈されました。
20周年とは、感慨深いものがあります。
第2問
大小二つの定規があります。大きい方は7cm、小さい方は3cmの目盛があり、それぞれ、中間の目盛がなく、7cmと3cmしか計測することはできません。この2つの定規を使って、できるだけ効率的に15cmの直線を引きたい。どうしたらよいでしょうか。言葉で説明をしてください。
正解は 7㎝の定規で3回、21㎝を図り、3㎝の定規で2回(6㎝)戻れば、15㎝が図れる。
当初、もう少し難しい問題だったのですが、校正段階で直したところ、やけに易しい問題となってしまいました。本来は7㎝と3㎝からいろいろなサイズを作成して、回答するはずなのですが、7と3だけでできてしまいました。
この手の問題は、3と7を使って、ほかの数字をどう作るか、というのがミソです。今回3と7だけでできてしまったのは出題者の不備でもあります。今回の15㎝を16、17、18と変えて作成してみますと、頭の体操になるでしょう。
類題として、大きいバケツと小さいバケツで、○○リットルを作る、といった問題もあります。考え方は、同じでいいはずです。
第3問
次の文章は、ある日本の街を説明したものです。よく読んで、どこの街か、○○県□□市(町村)のように、答えてください。
この街は、県の最東端に位置し、人口では県下5番目に当たる。古代には製鉄が盛んで、現在も金属の会社が立地している。市の魚は「どじょう」で、市の公式キャラクターは「あらエッサくん」である。日本画家の大家のコレクションと壮大な日本庭園を有する美術館がある。
正解は 島根県安来市(やすぎし)
正解にたどり着くのは簡単だったと思います。
第1のヒントは「製鉄」。古代の製鉄は、「たたら」という巨大な送風装置を使った、奥出雲地方の「たたら製鉄」がまず、頭に浮かびます。古代川砂に混ざる砂鉄を使って、製鉄が盛んとなり「出雲」の権力の源泉となりました。現在ある会社は「日立金属」で、「和鋼の博物館」を併設しています。
第2の「ヒント」は「どじょう」。昭和の宴会芸の花形「どぜうすくい」(安来節)も、今や見かけることも少なくなりました。昭和の時代、高度成長期の大企業の忘年会、熱海や鬼怒川などの温泉旅館の大広間で、数百人規模の大宴会でありました。その際の宴会芸として「どぜうすくい」がよく見られました。テレビのニュース映像で見た記憶もあります。「どぜうすくい」を今に伝える伝承館(安来節演芸館)が足立美術館の敷地(駐車場)の一角にあります。
大家の画家とは「横山大観」。美術館は「足立美術館」。創立者の足立さんが、名古屋で開催された横山大観展を見て触発された、との記述があります。広大な日本庭園と日本画の大作を中心とした美術館です。観光バスで団体客が続々と乗り付けます。安来駅前から無料のバスが出ており、私のような個人の旅行客でも行きやすいところです。
その他、安来市には戦国時代以前の豪族尼子氏の居城「月山冨田城」が残っています。この城は、一度も落城したことがないと言われる名城で日本百名城にも指定されていますが、訪れるのは極めて不便です。戦国以降は、松平氏の「松江城」が出雲地方の中心になっていきます。
以上、3問の解説。冒頭既述したように回答者全員が正解で、抽選は厳しい門となりましたが、7月中旬に抽選会を行いました。結果、碧南市のSさん始め5名の方に、図書カードなどの賞品を発送しました。当選者の皆様、おめでとうございます。外れた方も、次回は当たるでしょう。またのご応募をお待ちいたしております。